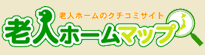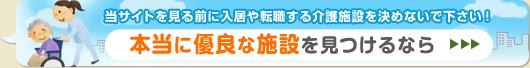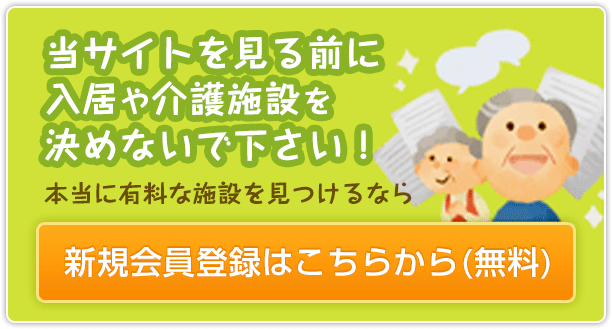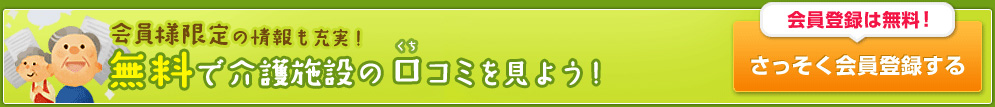日常生活で行う動作の1つ、起き上がりの介助法とは
起き上がりを介助する時に必要なのは…
寝返りがマスターできたら、次は起き上がりにチャレンジしましょう。
寝返りの場合は、介助を必要としない人の動きを参考にしましたが、起き上がりの場合は、応用ができません。なぜなら腕の力と腹筋を使って起き上がるからです。
要介護者は力が弱ってきているため、腕だけでは体を支え切れないので転倒する可能性があります。また、介助をする時も腕と腹筋だけの動作をサポートする介助方法(両手を引っ張る、頭を持ち上げる)は適切ではありません。
お互いに負担が大きい介助方法では苦痛しか残らないからです。
要介護者が無理なく起き上がれる条件を整え、その動きをサポートするような介助方法を施し寝たきり状態にならないようにしましょう。
自ら起き上がるためには、起き上がるパターンを見つけることが大切です。一気に起き上がるのではなく、できることを確実にこなし、段階を踏みながら起き上がりますので、筋力は少なくて済みますが、多少の腕の筋力は必要です。自ら起き上がることができるか、要介護者に筋力が残っているのかテストしてみましょう。
そのテストの方法は、要介護者と握手をしてみることです。
握り返してくる力で握力がどの程度残っているかが分かります。
痛いくらいでしたら自ら起き上がるための筋力はまだまだ残っているということです。
握力をチェックしたら次は、起き上がりのパターンを確認しましょう。
自ら起き上がるためのポイントは…
全ての介助方法は、日常に行われている動作を参考にしていますが、若く筋力がある人の動きを模倣するのは難しいものです。
しかし、妊娠している方や腰痛の方は、お腹や腰に負担が掛からないように起き上がります。この場合の起き上がり方は大きな力を使う必要がないので、筋力が弱った要介護者でも参考にすることができます。
起き上がりの一連の動作は、以下の通りです。
(1)膝を曲げる:起きたい方向の逆側の膝を曲げます。
(2)起きたい方向へ体を倒す:曲げた足を起きたい方向へ倒します。その時、体も同じ方向に倒します。
(3)足を揃える:両足を揃え曲げる
(4)腕に力を入れる:両腕を片側に付き徐々に力を入れる。体の下側にある腕は、徐々に伸ばし体を起こしていく。
(5)上半身を起こす:上半身が起き上がってきたら片側に付いていた手を体の両側に置く。
(6)足を伸ばす:曲げていた足をまっすぐ伸ばし起き上がり完成です。
焦らずゆっくりと体重を移動させながら起き上がりましょう。
介助者は、上記の動きに沿って体を支えたり、少し力を加えたりするような介助をしましょう。
関連記事
・日常生活で行う動作の1つ、起き上がりの介助法とは
・四肢マヒでも介助が楽になる方法とは?
・下半身マヒでも自らの力を使って寝返ることはできる?!
・片マヒだからと言って寝たきりになるのは当たり前というのは嘘
・たった3つの動作だけで寝返りの介助が楽になるって本当?
・介護は特別なことではない!日常の動作から学ぶ負担の掛からない介護とは
・夫婦で一緒に入浴する方法とは
・手を離すのが怖いという方への介助方法
・浮力を利用すると力を入れずに浴槽から出ることができる。
・安定して浴槽につかるには、前かがみの姿勢を保つことが大事
Facebookをされている方は以下より「いいね!」して頂ければ、定期的に情報を配信致します。