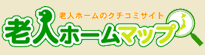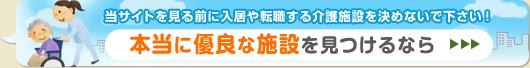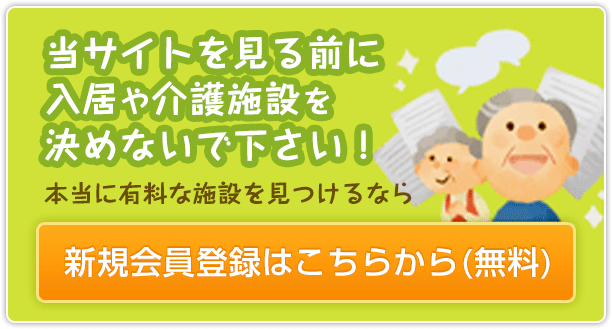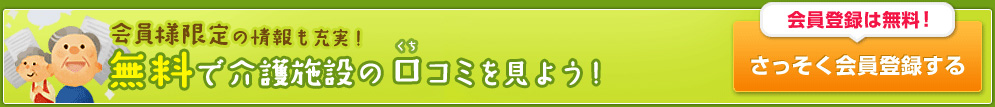-薬物有害反応-高齢者が薬物を投与されることで起きる薬物有害反応で生じる認知症と認知症様症状は3種類
高齢者が薬物の投与によって、非可逆的な認知症を来すことは、一部の抗がん剤や抗糖尿病薬を除くと少ないとされ、睡眠薬や抗精神病薬などが投与された場合には、副作用として認知症のような症状が、可逆的に引き起こされることがあります。
高齢者の薬物有害反応は、加齢に伴う生理的ないしは病的老化によって、①肝臓や腎臓の排泄機能が低下して、薬物の体内蓄積が進行する、②身体的な有病性が高まり、その影響で薬物動態の変化が生じる、③薬物に対する中枢神経系の認容性が低下することが原因と考えられています。そして、臓器への薬物曝露性や脳の薬物感受性が高まることから、薬物有害反応が多く出現するようになると考えらます。
高齢者が薬物を投与されることで、≪1.薬物誘発性認知症≫、≪2.薬物誘発性意識障害≫、≪3.薬物誘発性うつ状態(仮性認知症)≫といった、薬物有害反応によって認知症や認知症症状が引き起こされることが少なからずあると言われてます。
≪1.薬物誘発性認知症≫は、ビタミンB1欠乏によってコルサコフ症候群を引き起こすアルコール、抗がん剤のうちメトトレキセートやカルモフールなどによる白質脳症や抗糖尿病薬が低血糖による非可逆的な認知症を引き起こし、吸入麻酔薬、鎮静剤、睡眠薬、抗不安薬は、可逆的な認知症を生じさせることがあります。
高齢者の薬物誘発性認知症の発現には、①薬物の血中濃度が上昇したり、血中半減期が遠領する(薬物動態学的要因)、②脳の薬物感受性が亢進する(薬物力学的要因)、③脳内の薬物濃度が上昇したり、薬物による脳内環境が乱れやすくなる(生理的加齢要因)という3つの要因が、薬物の作用を強く発現させることになり、ドパミン神経系、アセチルコリン神経系、GABA神経系などで働く神経伝達物質を介して、記憶障害、注意力障害、認知機能障害が引き起こされることに関連していると考えられています。
≪2.薬物誘発性意識障害≫は、抗パーキンソン病薬、抗うつ薬などの抗コリン薬によるものが多く見られ、H2拮抗作用を持つ抗潰瘍剤、テオフィリンなどの気管支拡張薬、抗不整脈薬、ステロイド剤、抗利尿薬などがあります。
高齢者では、若年者では意識障害を引き起こすことのない通常量の服薬でも、意識障害を生じ易いとされており、その原因としては、①脳の加齢変化に伴う中枢性コリン神経系の変化、②ホメオスタシスの低下、③視力や聴力の低下、④薬物代謝機能の低下によると考えられています。
≪3.薬物誘発性うつ状態(仮性認知症)≫では、高齢者のうつ病の特徴が、活動性の低下や反応の鈍さなどの身体的表現を取ることで、うつ状態であるとわかりにくいために、認知症と判断されることがあります。仮性認知症は、症状の持続期間がうつ状態となっている期間に限定され、症状に軽快と憎悪の波がある、見当識が保たれている、物覚えの悪さを悲観しているなどから認知症と鑑別されます。
うつ状態を誘発する可能性が見られる薬剤として、インターフェロン、副腎皮質ホルモン、シメチジン(抗潰瘍薬)、ジギタリス(心不全治療薬、不整脈薬)、イソニアジド(抗結核薬)などが、高齢者に多く処方されています。
702212
関連記事
・認知症のBPSDのために行われる薬物治療の進め方とポイントとなる薬物治療検討のための4つの条件
・認知症の治療は薬物治療を検討する前に認知症ケアやリハビリテーションの介入をまず考慮
・認知症の鑑別診断で中心となるのは神経心理検査による診断で画像診断は補助的診断
・認知症高齢者のいのちを保つため認知症の進行を抑止するためには心地好い口腔ケアが必要?
・認知症高齢者の活動性低下を防ぐにはフレイルティ・サイクルを断ち切るのが一番?
・認知症高齢者の低栄養の原因は認知症のために美味しく・楽しく・心地好く食事が出来なくなること?
・-便秘-認知症の高齢者の便秘予防や対策に特に必要と考えられる4つの配慮
・-脱水-高齢者が脱水症になりやすいのは若年者に比べると体内の水分量が不足して脱水になってるから?
・-軽度認知障害-認知症の早期発見・早期治療のために期待されている軽度認知障害の有症率は11~17%
・-特発性正常圧水頭症-原因疾患が特定出来ない60歳以上の高齢者に起きる正常圧水頭症
Facebookをされている方は以下より「いいね!」して頂ければ、定期的に情報を配信致します。